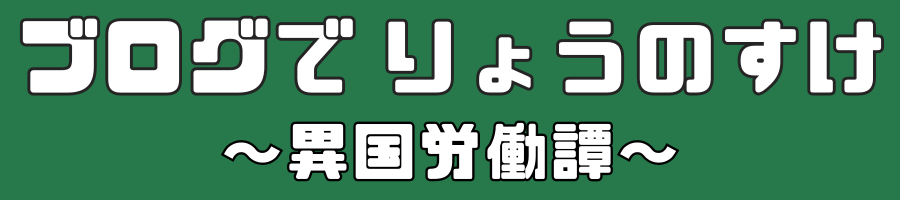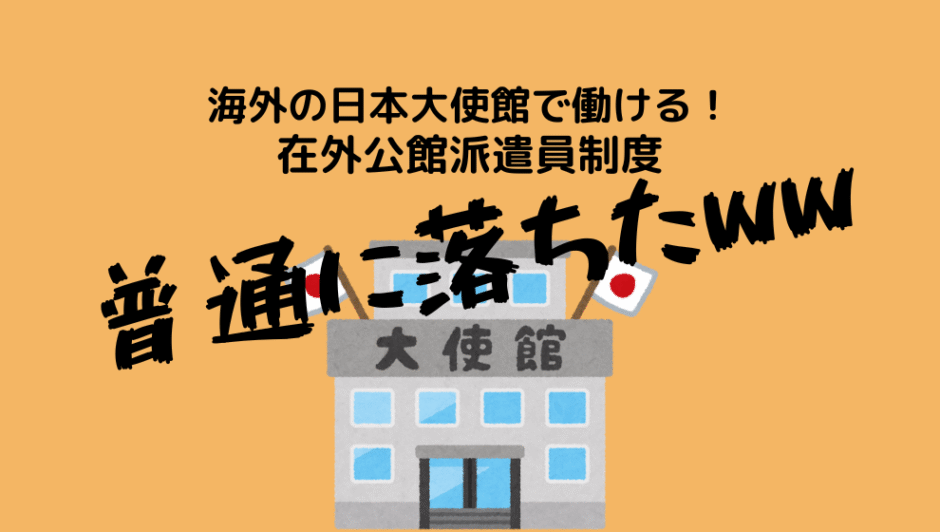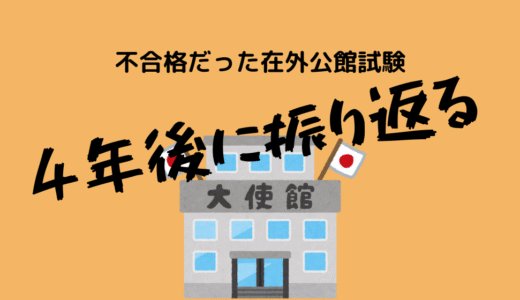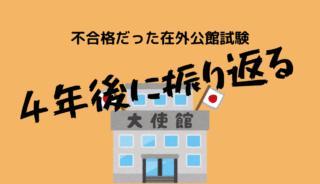「海外で働きたいな〜」「海外にある大使館で働く制度あるの??」
海外で仕事したいけど、なかなかうまくいかなかった時の話。
コネも何もない自分はとにかくネットを漁りまくり、そんなこんなを調べてる時に見つけた「在外公館派遣制度」。
筆者は在外公館派遣制度の一次試験を受けてきました。
在外公館派遣制度とは、一般社団法人 国際交流サービス協会のホームページを詳しく参照して頂ければいいのですが、
簡単に説明すると海外にある日本国大使館に2年間お仕事できるという制度です。
当時は、コロナウィルスのおかげで選考自体が中止になるかと思っていましたが、無事実施されてひとまず安心しました。
まぁでも試験日は延期になり、第一志望の在外公館も受け入れ中止になりましたけどね。
本記事では、僕が当時海外就職を目指していた時に第92回在外公館派遣制度一次試験を受けたので、その概要を紹介していこうと思います。
タイトルの通りですが、まあ普通に落ちてます笑
なので、失敗事例として参考にしてもらえると嬉しいです!
こんな人におすすめ
・これから試験を受けようと思っているけど初めてで全体概要を理解したい。
・落ちたやつを知って少しでも安心したい。
今回はあくまで筆者の備忘録であり、読者さんが今後受験するにあたり少しでも参考になればと思い執筆しました。また、こちら記事内容は以前作成した2020年6月の記事がベースとなっています。最新の内容は一般社団法人 国際交流サービス協会の情報を参照ください!
在外公館派遣制度とは何か?

在外公館派遣制度(在外公館派遣員制度)ってなんぞですか。
もし初めて聞きましたという方のために外務省より。
日本政府が海外の在外公館(大使館・総領事館・政府代表部・領事事務所 等)に対して、民間人材を派遣する制度。(在外公館派遣員制度について)
まあ、冒頭でもお伝えした通り、海外にある大使館などで働ける制度ですね。
厳密に言うと、国際交流サービス協会が募集して、採用した人材を外務省(在外公館)へ派遣している制度となります。
なのでこの制度を通じて行う仕事は、外交官としてではなく、派遣員として「後方支援業務」や「官務補佐」を中心に実務を担当するといった内容になります。
それでも、大使館などで勤務しながら海外勤務の経験が積めるなんてすごく魅力的ですよね。
在外公館派遣はその中でもいくつかの種類が提供されています。
在外公館で働く人材区分
在外公館派遣はその中でもいくつかの種類が提供されています。

- 派遣員
会計・総務的な業務、日本からの出張者支援など、外交活動を多方面から支える。 - 専門調査員
派遣国・地域の政治、経済、文化等に関する調査・研究を担当。 - 技術派遣員
在外公館施設の保守・整備・維持管理や、公館新設時の施工管理を行う。 - 公邸料理人
在外公館長(大使・総領事)が催す食事会で提供する料理を担当。
僕はこのなかで、派遣員の試験を受けたのでこの記事では派遣員に絞って紹介します。
制度の歴史と目的
- この制度はが始まったのは 1973年(昭和48年) 。
- 当初は日本人が海外で働く機会が限られていた時代、若手人材に国際経験させる目的で発足。
- これが現在でも定期的に募集が行われ(年2回程度)、制度は長期にわたって継続され今に至っている。
この制度が掲げる主な目的・役割については下記になります。
- 外交活動の補佐・支援
派遣員は外交官・在外公館スタッフを補助し、館務運営や庶務・旅費調整・来客対応などの業務を担当。 - 国際経験・語学力の活用
海外勤務を通じて、語学力だけでなく外国文化・社会を直接体験する機会を提供。将来の国際キャリア育成につなげる狙いがある - 在留邦人や公館来訪者の便宜供与
在外公館にアクセスする日本人や公用訪問者のため、空港送迎、滞在手配、旅程補助などの業務がある - 友好親善・日本のプレゼンス強化
文化交流事業支援や現地との関係を通じて、日本の国際的プレゼンスを高める役割も期待されている。
応募対象者・応募条件
派遣員制度に応募するための主な条件・制約は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国籍 | 日本国籍を有すること。任国の国籍・永住権等を保持する者については制約あり |
| 学歴 | 高等学校卒業以上が基本要件 |
| 年齢 | 制度上の明示的な年齢上限は記載なし |
| 語学力 | 派遣先国の言語(または英語)能力が求められる。語学試験が選考に含まれる |
| 自動車運転免許 | 派遣先によって普通自動車運転免許を要件とする募集がある |
| その他 | 健康状態、滞在許可・査証取得可能性等、赴任先での生活・法的要件を満たすこと |
募集・選考の流れ
以下は一般的な募集・選考の流れです。
一次試験は毎回大阪・東京の2拠点のみで実施されているので遠方の方は注意が必要です。
- 募集公示
国際交流サービス協会が外務省の委託を受けて、年2回(多くは5月・10月)に募集開始。 - 応募書類提出
履歴書・志望動機書・語学証明書などを提出。 - 一次試験
外国語試験、一般教養、適性検査の実施。*どの言語で試験を受けるか応募時に選択できる - 二次試験
外国語面接・日本語面接など。面接で語学力や人柄・志望動機などが問われる。 - 内定・赴任前研修
合格後、研修を経て赴任先が決定。 - 赴任・勤務開始
一般社団法人 国際交流サービス協会のサイトを拝見すると、募集期間・一次試験・二次試験のスケジュールが公表されています。
業務内容はどんな感じ?
派遣員の業務は派遣先・部署によって詳細は変わるとのことですが、
HPによると、概ねの業務は下記となるようです。
- 便宜供与
外交官(及び家族)の着任、離任支援
着任時
・空港出迎え(入国支援を含む)
・生活の立ち上げ支援(住居探し、自動車購入など)
離任時
・航空券手配
・税関手続き手伝い
・空港見送りなど - 官房班などでの館務事務補佐(主に在外公館の運営にかかわる調整業務)
・会計業務補佐
・配車(現地職員ードライバーのスケジュール調整など)
・航空券予約(館員の出張手配・休暇帰国手配)
・物品管理(公館で使用する備品等の購入など)
・館内会議資料作成
・休暇簿(出勤簿)管理 - 領事業務
・旅券・査証発給の事務補助
・邦人援護(大規模災害、事故が起きた際の邦人安否確認業務における通訳・翻訳等) - 広報文化業務(注)赴任先公館によっては全く担当しないケースがある
・在外公館ホームページの更新
・広報文化イベント業務の事務補助(日本祭り、日本語スピーチコンテストなど大型イベントの運営補助)
ちなみに、体験談をもとにしたブログ(【経験談】外務省在外公館派遣員)を見ると、派遣員はあくまで外交官のサポート役であり、
外交交渉そのものには直接関わらないと述べられています。
雇用形態・待遇など
雇用形態や待遇などについては下記にまとめました。
参考ブログ
「在外公館派遣員ってどんな仕事?試験の流れから現地での生活まで徹底解説!」
- 派遣員は正規の外交官ではなく、嘱託・契約社員・派遣労働者という形態になる。
- 給与に加え、手当(住居手当・渡航費補助など)が支給されることが多い。
- 勤務時間・残業・休日などについても法令に準拠する形で定められている。
- 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などに加入する制度となっている場合があります。
- 任期は延期されることもあるようですが、原則2年 とされることが多いです。
在外公館派遣で働くメリット・デメリット
メリット
- 国際経験を積める:異文化の中で働く経験、語学力を伸ばし稀有な経験を得れる
- キャリアの幅を広げられる:外交・国際関係・公共政策分野などの経験から次の国際キャリアに進める
- 日本と世界をつなぐ役割を体感:在外公館として日本を代表する仕事に関わる実感が得られる。
- 支援制度が整っている:赴任・住居・渡航という生活基盤面での補助が見込まれる。
デメリット
- 待遇・安定性の不確実性:国際キャリあるあるだが、派遣なので安定はしない。
- 生活環境の変化・負荷:言語・文化・気候・医療など、慣れない環境での生活。
- 業務負荷・マルチタスク性:人員が限られるため、多様な業務を兼任するケースが多いという経験談もある。
- 外交の意思決定には関与しにくい:あくまで補助業務が中心で、外交政策には直接関われない。
帰国後・キャリアパス
この在外公館派遣が終わったら、経験は次どんな進路に進むのでしょうか。
この制度への送り出しは神田外語大学が以前から力を入れているようでそこから情報をとってきました。
- 大学へ復学して卒業後の進路を探す(学生時代の派遣者)
- 企業やNPOなど民間で国際関係・公共政策分野での仕事
- 大学院進学
- 外務省等の公務員試験を受けて外交・国際機関を目指す
- 赴任国での就職や地域に根差した仕事を選ぶ
派遣員経験は政府関係や、ボランティア、国際機関へキャリアが伸びることが多いんでしょうね。
外務省在外公館派遣員のすゝめ~外務省在外公館派遣員制度とは~
実際に受験した体験談
ではここから私の実際に受けてみた経験談を始めたいと思います。
特に大阪で受験する人に参考になったらいいです。
が1000回くらい言及してますが、私落ちてます(血眼)
試験日の朝
試験の当日。
私は大阪在住だったので大阪会場で受験することになりました。
試験会場は西梅田にあるビルでJR大阪駅からは大体徒歩10分くらいで着きます。
会場は9:15から開くということだったので、9時くらいに会場のビル前に着くように向かったのですが、到着するとビルの入り口付近には既に試験を受けるであろう人達が何人も立っていました。
ちゃんと数えてないですが、50人くらいはいたんじゃないでしょうか
一次試験の語学試験は応募段階で指定ができるのですが、私は英語を選択しました。
英語を指定した人は14階、他の言語を選択した人は15階が試験会場となっていました。
試験の概要は以下のとおり。
- 英語筆記 60分
- 一般常識 30分
- 適正検査 75分
*各テストの間に10分程度休憩が入る。
次に各試験を受けた感想を記述していきます。
英語筆記 60分
受けた感想としては、TOEICを少し簡単にしたような内容でした。
これは前例を残してくださっていた他のブログ執筆者さん達の言う内容と相違ありませんでした。
形式はマークシートで短文の穴埋め・会話文の穴埋め・文法正誤・長文問題に分類。
ウェイトは長文問題が全体の1/3を占めている印象でした。
全体的にTOEICと傾向が似ている一方で二つの穴埋め問題はどちらかと言うと、「文法的に正しい解答」をというよりも、「文脈的に適切な解答」を求める問題となっていました。
なので、「Hi ポール!昨日頼んだプレゼン資料できた?」みたいな質問には「すごい天気がいいねぇ!」でなく「今朝完成したよ!」といった文章を当てはめなければなりません。
すみません。これうまく説明できないっす笑
心が荒んでいる人は、問題を見て「この解答入れても会話は成立するじゃん!!」などと思ってしまうかもしれませんが、
あくまで文脈=一般的に考えられる無難さに違和感がなく普通であることが大事なので、
くれぐれも捻くれた思考はしないようお願いします。
普通ってなんでしょうね。
次に、文法正誤の問題は、短い文章中の単語に下線がいくつか引かれており、その中で文法上誤りとなる単語を選ぶというものでした。
イメージ的にはaffected となるところが affecting となっていたり、opportunitiesと複数にするところをopportunityと単数で表記されていたり、といった感じです。
文法正誤の問題に関しては、英字ニュースなどを日頃から読むようにしていれば文章の違和感に気付きやすくなるかもしれません。
最後に、長文問題はそのままTOEICの長文問題を連想していただいてほとんど差し支えないかと思います。
TOEICで時間が足らないとこの試験でも同様に時間が足らなくなると認識しておいた方が良いでしょう。
長文問題はTOEIC同様に文中キーワードを早く見つけ、不要な部分は読まず短時間で解答することが重要だと考えます。
ちなみに筆者はTOEICでも最後まで時間を余らして終えたことがないので今回も10問分くらいマークを適当に塗り絵する惨めな結果となってしまいました。
TOEICのテスト本を買って準備しておいた方がいい
上述しましたが、テストの時間が結構シビアです。
なので、深く理解できる英語力と同時にポイントを押さえて解答できるトレーニングもしておきましょう。
この辺は教材の好みあると思うので実際に探してもらった方がいいと思います。
とにかくポイントは、「模試」「時間内に解答できるテクニック」
在外公館受けるくらいのみなさんなら「TOEICなんて鼻で笑っちゃうくらい簡単だぜ」
とお思いかと存じますが、もし最近テスト受けてなくて少しでも心配なら絶対準備しといた方がいいです。
一般常識 30分
お次は一般常識試験ですが、まず一言。
まじで時間足りん。
問題は60問。それに対して時間は30分しかありませんでした。
受験した後に気づきましたが、全問しっかり解答しようなんて思わずに、答えに自信がある問題以外は全部スルーした方がいいかもしれません。
わからない問題や時間がかかりそうと思った問題は終了5分前に塗り絵タイム(適当に解答埋める)で神頼みして、
確実に正解を出せる問題の母数を増やすべきだと思いました。
なぜなら時間がなさすぎて問題前半に時間をかけると、最悪の場合、後半の問題をノールックで塗り絵しなければならないからです。
答えを知っている問題を落としてしまうのは非常にもったいないです。
問題内容は、政治・経済・物理・数学・時事問題・地質学・化学・歴史・国際情勢など多岐にわたる分野から平均5問ずつくらいだったかなぁと思います。
他の受験者がどのように対策しているかわかりませんが、いくつか特化する分野をいくつか定めて集中的に勉強した方が実は高得点出せるんじゃねと思いました。
少なくとも筆者はどれだけ頑張ってもあの問題全てを解くことは物理的に無理だと悟りました。
テスト傾向から見た買っておいた方がいい本
正直なところ、あまり勉強しなかったですが、本はいろいろ書いました。
その中でこの試験の内容にマッチしてる本だけ紹介します。
この二つは結構内容的にも適しているかなと思います。
ですが、他にも一般常識の本は売っているので是非ご自身で見てみてください。
次に出題傾向が一番近いと感じたのは二個目に貼った「一問一答」かなと思います。
しかし、個人的にすごい勉強しづらい書式スタイルだったので過去問本みたいな使い方するのが良いと思います。
他のブログでは、稀に一般常識試験の勉強はSPIの対策本で良いと思うという意見も拝見します。
がこれについては個人的な意見なのですが、
受験を経験した身としてはSPIは出題傾向がかなり異なるので買うべきではない気がします。
非言語のような数学の勉強をすることについては、SPIでの勉強も有効と言えるかもしれません。
がしかし、数学が苦手なら他の分野の勉強に焦点を当てた方が結果的に高得点を狙えるのではないかと考えられます。
適性検査(小論文と心理テスト) 75分
最後に適性検査試験です。
適性検査といっても内容は大きく、小論文系の時間と心理テストの時間に分けられています。
小論文が60分で心理テストは15分くらいの内訳だったと思います。
小論文とかのテスト
A4一枚裏表
・小論文的な記述
・希望の公館とその志望理由15文字
・小作文
・今の自分のきもちに近いのを番号つけてくやつ
小論文的な記述
内容は、「自分の弱みとか克服したことを体験交えて書いて」的な内容でした。
筆者は社会的に底辺の人間ですが、一応修士号取得者なので文章はまあ及第点くらいは書けたかなといった手応えはありました。
最初の文で自分が何を克服したいかを端的に書いて、実際にどういうエピソードがあったかを実例として書き、最後にそれっぽい締めの段落を書いた感じです。
希望の公館とその志望理由15文字
志望理由は特に準備せずその場の思いつきで書きました 。
以外とわかりやすく要約ができるかなどを見ているのかもしれません。
小作文
自分が赴任した姿を想像してどんなことしてるか好きに書いて」的な内容でしたが、小作文の内容は、先人のブログを見るにずっと同じのようです。
小作文も好きに書いていいよって感じだったので誤字脱字や主語述語に気を付けて書きました。
今の自分のきもちに近いのを番号つけてくやつ
自分の今の気分に近いものを以下から1〜10の順番でつけていってください
優先順位に沿って順番をつける心理テストもその場の感情に身を委ねて書きました。
このテストも大事だとは思うのですが、小論文に比べると優先度が低いと思うので時間配分のウェイトはあまり置かない方が賢明かと思われます。
心理テストと図形に絵を描く心理テスト
よくある心理テスト。
合否に大きく関わると思いますが、ゴマ剃った内容によせると結果がおかしくなるらしいので正直に答えた方が吉かと思われます。
〜図形に絵を描くテスト
よくわからなくて何書いてもいいということだったので、直感的に書きました。
受験した手応え〜まとめにかえて
今回受験した手応えとしては
英語筆記:微妙
一般常識:爆死
適性検査:なんとも言えん
な感じでした。
英語筆記はTOEICとかで早く解答する練習しとけばよかったなと思ったものの、あの英語そのものの力量でなくテクニックで解いていく感じがあんまり好きじゃなんですよね〜。
英語に関しては学生時代の方が解けたかも。
一般常識に関しては爆死以外の表現が使えない。
悲惨すぎてもはや全く落ち込まない。
テスト前に勉強しなさすぎて逆に謎の自信が湧いたけどやっぱりテストおわた!!の時のアレ。
次受けるなら上述したように、特定の分野を絞って集中的に勉強しようかなと思います。
個人的には四字熟語、物理、地質、SPIの非言語問題は即捨てして、
国際情勢、時事問題、政治、経済、日本史、世界史あたりに絞ります。
得意な分野7つくらいで正解できれば、正答率半分は超えて相対的な高得点は十分確保できるかと思われます。
適性検査は可もなく不可もなくってゆう手応えです。
ただ、小論文と作文は、誤字脱字と主語述語といった文法と段落の構成は意識して取り組むといいかもしれません。心理テストはノリ。
さて結果は1週間後に来るのでどうなることなのか。二次試験進めたらいいなぁ〜期待してへんけど。
P.S 今回はコロナウィルスの影響で説明会が開催されないこともあり、情報が集めにくかったので、ブログの在外公館経験者のブログ以外にも以下の「大使館ガイド」という本も書いました。概要自体はネットに十分な情報が書かれているので特に必要ないですが、何名かの大使館勤務の経験談が集録されているのでそれ目当てで購入しました。気になる方は読んでみてください。
2020.6/25 追記
試験の結果が返ってきましたが案の定不合格でした。
薄々分かっていたものの、やはり悔しいのでまた、秋募集で挑戦したいなと考えています。
*結局応募してません笑
2024.6/13 追記
結果在外公館派遣員試験は受けてないです。コロナで海外出れる機会が少なかったので、国内で3年勤務して夏前から海外で働きます。おいおいその辺りもお話できればと思います。
振り返り記事更新しました。もちろん勉強も大事ではありますが、もっと根本的な部分の見直しも必要だったかもなと思ったり。
*追記2025年現在でも閲覧いただいてありがとうございます。
合格はしなかったものの、いろいろ回って今ベトナムで仕事しております!
その経緯も記事にまとめようと思うので、しばしお待ちください!
少しでもこの記事が誰かの役に立っていると嬉しいです。
頑張ってください!